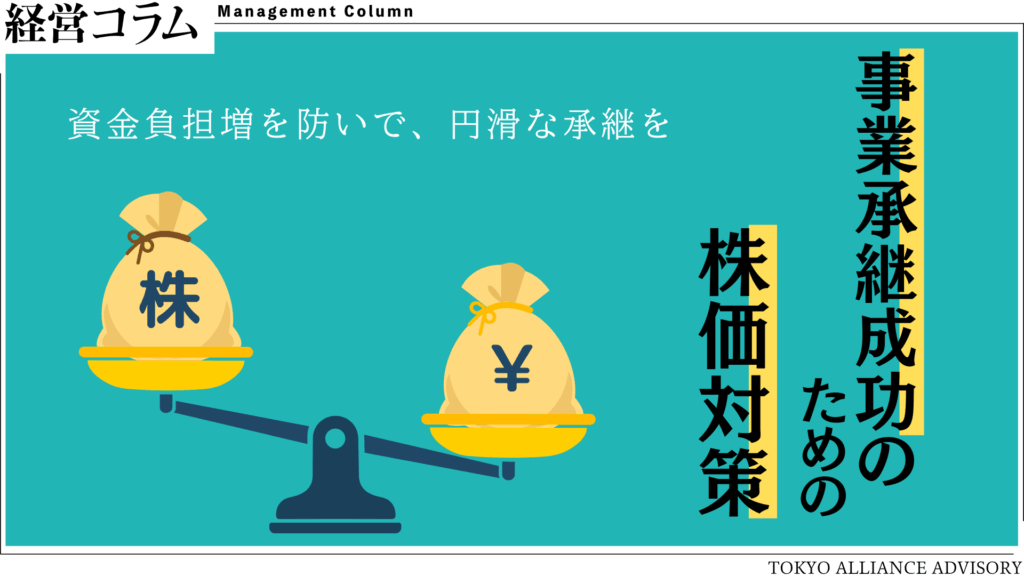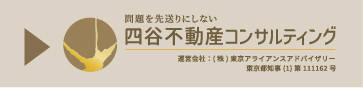事業承継にあたって株価を下げるのは、後継者の承継意欲を高め、経営基盤を安定させた状態でバトンを渡すために必須の措置と言えます。ここでは、その重要性から具体的な株価引き下げ方法、メリット、注意点まで、円滑な事業承継を実現するための戦略を詳しく解説します。
事業承継における株価対策の重要性
事業承継を成功させるためには、自社株式の評価額(株価)対策が不可欠です。とくに中小企業のオーナー経営者にとって、株価の高さは事業承継の大きな障壁となり、後継者候補に承継を敬遠されることにもなりかねません。
株価が高いとなぜ問題なのか
非上場企業の株価が高いと、事業承継時にさまざまな問題が生じます。中小企業の形態として多い同族経営で生じるのは、相続や贈与による株式移転時に高額な税金が発生し、後継者に大きな負担を強いる問題です。後継者候補以外にも相続人がいるケースでは、現経営者の個人資産に占める議決権付き株式の評価額の割合が大きくなることで、結果として遺産分割の割合が不公平になり、これを解消するために資金の追加または株式分散を許容することになりかねません。
第三者承継(従業員承継)を目指すケースなど、贈与ではなく有償での株式移転を目指すときにも、株価が高いと問題が生じます。多額の資金調達が必要となり、個人保証や担保提供などのリスクにさらされるのです。この問題を回避するための手段として金庫株(自社株買い)を利用した場合においても、会社の資金流出により財務基盤が弱体化するリスクを看過できません。
株価対策で得られるメリット
事業承継を予定する中小企業(とくに業績好調な企業)にとって、株価対策は必須と言えます。移転する株式の評価額の低下は、事業承継全体にかかるコストの引き下げにつながります。ここで挙げるメリットは、後継者候補の意欲を高め、円滑な事業承継の実現につなげることもできるでしょう。
▼親族内承継における株価対策のメリット
……生前贈与や相続によって親族内承継を実施するケースでは、節税に加えて相続トラブル(遺留分侵害額請求など)の防止効果もあります。後継者の資金負担を減らしつつ経営意欲の低い少数株主の出現も最大限回避できることで、経営の基盤・方針に大きな変更を生じさせることなくバトンを渡せます。
▼親族外承継(第三者承継)における株価対策のメリット
……後継者側に求められる株式移転のための費用(買取費用)が少なくなることで、能力や価値観を重視した後継者選びが可能となります。承継後も会社および後継者の財政基盤をそのまま維持できることは、挑戦的な事業展開を可能にします。
非上場企業の株価評価方法を理解する

事業承継における株価対策では、株価の算定方法の検討が求められます。広く参考にされる評価方法として「類似業種比準方式」と「純資産価額方式」があります。ここでは、各方式の概要と、採用する方式に関する基本的な考え方を整理してみましょう。
類似業種比準方式とは
比較的規模の大きい会社に適用されることの多い「類似業種比準方式」は、評価対象の会社と事業内容が似ている上場企業の市場株価を基準に、非上場株式の価値を推定する方法です 。具体的には、類似する上場企業の平均株価に、評価会社の配当・利益・簿価純資産の3要素が、類似企業の各要素と比べてどの程度の水準にあるかを比率で反映させて計算します。
▼類似業種比準方式による評価の手順
- 上場企業の平均株価を判断する
- 比較要素(配当・利益・簿価純資産)について、上場企業に対する対象企業の割合を算定する
- 斟酌率(0.5~0.7)および資本構成調整を検討、反映する
純資産価額方式とは
小規模~中規模の会社に適用されることの多い「純資産価額方式」は、会社が保有する全資産と負債をを基準とする評価方法です。評価にあたっては、帳簿上の価格ではなく、評価時点での時価に近いとされる相続税評価額基準で評価し直し、その差額に基づいて株価を算定する方法です。計算上、資産の含み益に対して将来課されうる法人税等相当額(現行37%)を純資産から控除する点が特徴です。
株価算定の方法の選び方
事業承継における株価算定で採用する方式では、会社の規模によって基本的な考え方が決まります。ここで、税法上の評価方法のルールを参照してみましょう。
- 大会社:類似業種比準方式
- 中会社:類似業種比準方式と純資産価額方式の組み合わせ
- 小会社:純資産価額方式
株価算定での方式検討のポイントとなるのは、会社の将来性や市場環境など、さまざまな要因を考慮して最終的に決定される点です。たとえば、資産構成が特殊な会社(土地や株式の保有割合が極端に高い会社など)は、主に純資産価額方式が採用されます。
株価対策を実施するタイミングと注意点

株価対策は計画的に実施することが成功の鍵です。適切なタイミングで対策を講じなければ、十分な効果が得られないばかりか、税務調査で否認されるリスクも高まります。また、株価引き下げと会社の財務健全性のバランスを保つことも重要な課題です。
株価対策に着手すべき時期とは
株価対策はできる限り長期計画で、遅くとも事業承継実施前の5年前から実施したいところです。また、業績が好調な時期は株価が高くなりやすいため、この時期に対策を講じることで効果が高まります。
株価対策は一度に行うのではなく、段階的に実施することが重要です。急激な株価変動は税務当局の注目を集めやすく、否認リスクが高まるためです。また、2025年4月現在の税制を踏まえると、類似業種比準方式の計算式が改正され、利益圧縮による効果が以前より小さくなっているため、より計画的な対策が求められます。
税務調査のリスクを回避するポイント
株価対策が税務調査で否認されないためには、経済的合理性を示すことが不可欠です。役員報酬を引き上げる場合は、業績向上や責任増大など合理的な理由を明確にし、同業他社との比較データも準備しておくことが重要です。役員退職金の支給においても、退職金規程の整備や在任期間・功績に応じた算定根拠を明確にする必要があります。
同族会社の場合、同族会社の行為・計算否認規定により、不自然な税負担軽減行為が否認されるリスクがあります。そのため、株価対策は租税回避だけを目的とせず、事業の発展や円滑な事業承継など真の事業目的を明確にすることが重要です。
※具体的な株価対策については、主に下記の方法があります。詳細は別のコラムで解説します。
- 役員報酬の改定
- 退職金の活用
- 株式の配当金の見直し
- 生命保険、不動産購入、設備投資の実施
会社の財務健全性とのバランスの取り方
株価対策と会社の財務健全性は時に相反する関係にあります。利益圧縮による株価引き下げは財務指標の悪化につながるため、本業での安定した利益確保と株価対策のバランスが重要です。とくに自己資本比率は金融機関の融資審査において重視される指標であるため、過度な純資産の圧縮は避けるべきでしょう。
融資審査への影響を最小化するためには、株価対策の内容を金融機関に事前に説明し、事業承継対策の一環であることを理解してもらうことが効果的です。また、株価対策が従業員のモチベーション低下につながらないよう、会社の将来ビジョンを共有し、事業承継が会社の持続的発展につながることを説明する必要があります。
事業成長のための投資と株価対策は両立が理想的です。設備投資は減価償却費による利益圧縮効果があり、同時に事業競争力の強化にもつながります。株価対策と事業成長の優先順位を明確にし、会社の将来を見据えた戦略的な対応が求められるのです。
まとめ
事業承継における株価対策は、相続税・贈与税および株式取得コストの低減を通じ、承継の円滑化を実現するための必要な措置です。具体的な手法としては、株価算定の手法の検討のほか、役員報酬や生命保険の利用、設備投資、株式配当金の調整などが挙げられます。
最適な株価対策は、事業承継のスキームおよび企業の状況で異なります。貴社の実情に合わせた最適なプランは、東京アライアンスアドバイザリーにお任せください。