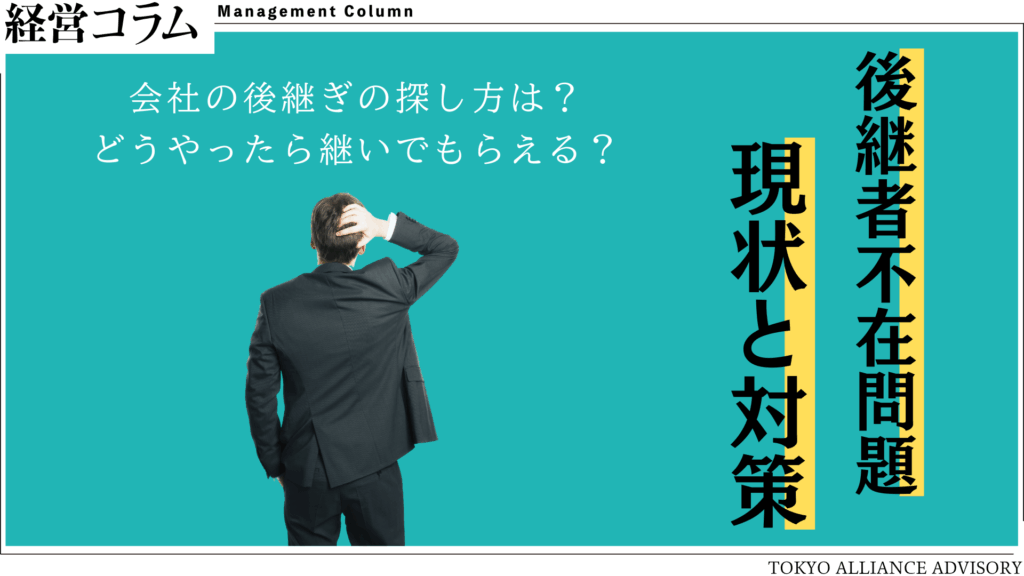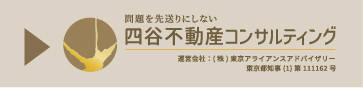日本の中小企業は深刻な後継者不足に直面しています。経営者の高齢化が進む中、多くの企業が事業承継の準備ができておらず、貴重な技術やノウハウ、雇用が失われる危機に瀕しています。ここでは、後継者を見つけるための方法に加え、事業承継を成功に導くためのポイントを解説します。
中小企業の後継者不在の現状
日本の中小企業は深刻な後継者不足に直面しています。経営者の高齢化が進む中、適切な事業承継対策が講じられないまま多くの企業が存続の危機に立たされており、この問題は日本経済全体に大きな影響を与えつつあります。
最新データで見る後継者不在率
帝国データバンクの2024年の最新調査(リンク)によると、日本の中小企業における後継者不在率は52.1%と高い水準です。業種別では、建設業や製造業が深刻であり、消費者の生活を支える卸売業・小売業などでも高い値が出ています。近年は後継者不在の打開策が官民ともに講じられるようになり、各業界の不在率の年次推移は下がりつつありますが、依然として予断を許さない状況が続きます。
※帝国データバンク「全国後継者不在率動向調査(2024年)」をもとに作成
高齢経営者が抱える2つの問題
高齢経営者が直面する第一の問題は、時間的制約です。後継者の育成にかかる時間は、業界と経営のどちらも経験がない候補者だと5年から10年程度、業界経験がある場合には少なくとも3年かかると見込まれます。実際に、過去3年間に代表者交代が行われた会社を対象とする前述の帝国データバンクの調査では、次のような結果が出ています。
■後任代表者の経験年数
- 業界経験10年以上:85.1%、
- 経営経験3年以上:26.1%(3年以上11.9%、10年以上14.2%)
経営者の高齢化に伴う第二の問題は、事業の継続性です。後継者不在のままでは、現経営者の健康状態の悪化を機に意思決定が停滞し、事業を続けられなくなるかもしれません。慌てて後継者を決定するケースでは、経営者が長年かけて築き上げた技術やノウハウ、取引先との信頼関係といった無形資産の継承が不完全となり、結果として企業価値が大きく毀損する恐れがあります。
後継者不在企業が選ぶべき3つの選択肢
後継者が見つからない中小企業には、大きく分けて3つの選択肢があります。親族や従業員への承継、M&Aによる第三者への譲渡、そして最終手段である計画的な廃業です。
親族内承継・従業員承継
親族内承継は、経営者の子どもや親族に事業を引き継ぐ方法で、事業への理解や取引先との信頼関係の継続性が高いメリットがあります。一方、従業員承継は社内の優秀な人材に経営を託すもので、事業内容や企業文化への理解が深く、スムーズな移行が期待できます。
いずれの方法でも、主な課題となるのは、会社の資産を移転させるために必要となる後継者の資金です。この点については、政府が実施する「事業承継・引継ぎ補助金事業」や融資による資金調達のほか、事業承継税制の活用による納税時期の先送りなどの方法を組み合わせる必要があります。
M&Aによる第三者承継
M&Aによる第三者承継は、親族や従業員に適任者がいない場合などの選択肢です。通常、M&Aのプロセスは、準備段階、買い手とのマッチング、基本合意、デューデリジェンス、最終契約締結の順に進み、半年から1年半程度の期間を要します。
計画的な廃業
事業継続が困難と判断される場合は、計画的な廃業も選択肢の一つです。廃業判断の基準としては、後継者不在あるいは経営者の健康状態以外に、収益性の持続的な低下・事業環境の構造的変化なども挙げられるでしょう。
廃業を決断した場合は、従業員への誠実な対応が不可欠で、退職金の支払いや再就職支援などの法的・道義的責任を果たす必要があります。債務整理においては、取引先や金融機関との早期の協議が重要で、資産処分では不動産や設備などの適正評価と効率的な換金が求められます。
後継者を発見する方法と支援策

後継者不在に悩む中小企業経営者にとって、適切な後継者を見つけることは喫緊の課題です。後継者の探索と事業承継については、さまざまな支援機関や制度が整備されており、これらを活用することで後継者発見の可能性があります。また、承継しやすい環境づくりや個人保証の解除問題への対処も重要なポイントです。
各種支援機関の利用
全国47都道府県に設置されている「事業承継・引継ぎ支援センター」では、専門家による無料相談や後継者マッチングサービスを提供しています。また、「後継者人材バンク」を利用すれば、経営意欲のある人材と出会える可能性があります。そのほか、商工会議所や金融機関でも、独自の事業承継支援を展開している場合があります。
民間で支援を得る場合には、中小企業庁においてM&A支援機関として登録されている会社を選ぶのが適切です。これらの機関では、後継者発見から事業承継のプロセスまでに必要な支援につき、実務の遂行まで支援を受けられます。
M&A支援機関の選択で重要なのは、自社の経営体制および状況に合ったアドバイスができるかどうかです。登録支援機関の数はすでに3,000件近くに上っており(リンク)、支援の方針や得意分野は多様化しています。経営者および自社の状況に沿った支援が得られるかどうかは相談先しだいと言えます。
承継しやすい環境を作るためのポイント
円滑な事業承継にあたっては環境整備が重要です。まず、正確な財務資料の作成に取り組みましょう。これにより、後継者候補や金融機関に安心感を抱かせることができます。
ほかに重要なのは、後継者にとってネックとなる要素の排除です。承継が敬遠される要素としては、経営者保証の存在、企業の強みおよび将来性の不明瞭さや、取引先および従業員との関係の不安定さなどが挙げられます。これらの要素を取り除くにあたっては、次のような取り組みが必要です(一例)
- 経営者保証の解除(後述)
- 経営資産の価値評価
- 取引先との関係の再確認・見直し
- 属人化している業務の洗い出しと対応
経営者保証の解除について
経営者保証(個人保証)の問題は事業承継の大きな障壁となりますが、「経営者保証ガイドライン」を活用することで解決の糸口が見えてきます。このガイドラインに沿って、財務状況の改善や経営の透明性向上に取り組むことで、保証解除の可能性が高まります。
また「事業承継特別保証制度」を利用すれば、後継者の個人保証なしで融資を受けられる場合があります。金融機関との交渉では、事前に財務内容の改善や事業計画の策定を行い、交渉の根拠となる資料を準備することが重要です。
事業承継を成功させるための3つのポイント

事業承継を成功に導くには、綿密な計画立案、円滑な引継ぎ実現、そして経営者自身の将来設計が重要です。これら3つのポイントを押さえることで、企業の持続的発展と経営者の安定した未来を両立させることができます。
現状分析から始める事業承継計画の立て方
事業承継計画の第一歩は、財務・法務・税務の現状把握です。資産と負債の詳細な棚卸しを行い、企業の実態を正確に把握します。
次に必要なのは、承継時期と方法の決定です。この際には士業およびコンサルティング職の選定が必要となり、選定にあたっては事業承継の実績や業界知識を重視しなければなりません。計画は現実的なタイムラインを設定し、5年後、3年後、1年後などの節目ごとに達成目標を明確化します。
後継者への円滑な引継ぎを実現する方法
円滑な引継ぎの鍵は、計画的な後継者育成にあります。まず、経営に必要なスキルを明確化し、それに基づいた育成計画を策定しなければなりません。権限移譲は「3年計画で徐々に責任範囲を拡大していく」など計画的に行い、具体的な時期設定を必要とします。
同時に、取引先や従業員への紹介も進め、後継者が自然に関係構築できるよう支援することも大切です。企業理念や経営哲学の共有には、日々の対話や重要な意思決定の場面で具体例を示すなど、継続的なコミュニケーションが効果的です。
経営者自身の将来を守るための対策
経営者の将来設計では、適正な株式評価に基づく譲渡対価の確保が重要です。後に得ることになる譲渡対価は、勇退後のセカンドライフを支え、さらに先の将来においては相続人の生活や事業継続のための資金となります。
また、現経営者の今後の生活を盤石なものとするため、退職金や年金計画を早期に立てることも不可欠です。会社の未来にとってより好ましい環境とするため、顧問や相談役として経験を活かしつつ、徐々に関与を減らしていくしくみを整えておくのも良いでしょう。
まとめ
後継者不在問題は、個々の企業だけでなく日本経済全体にとっても重大な課題です。しかし、適切な準備と計画があれば、さまざまな解決策が存在します。親族内承継、従業員承継、M&Aによる第三者承継、そして計画的廃業まで、それぞれの選択肢を理解し、早期に行動を起こすことが重要です。承継のプロセスに入る際には、企業価値を高め、承継しやすい環境を整えること、経営者保証の問題に対処すること、そして専門家の支援を活用することを意識しましょう。
事業承継は単なる経営権の移転ではなく、企業の歴史と価値観、そして従業員の生活を守る重要なプロセスです。経営者自身の老後の安心も確保しながら、次の世代へと事業をつなげていくための第一歩を今こそ踏み出しませんか。