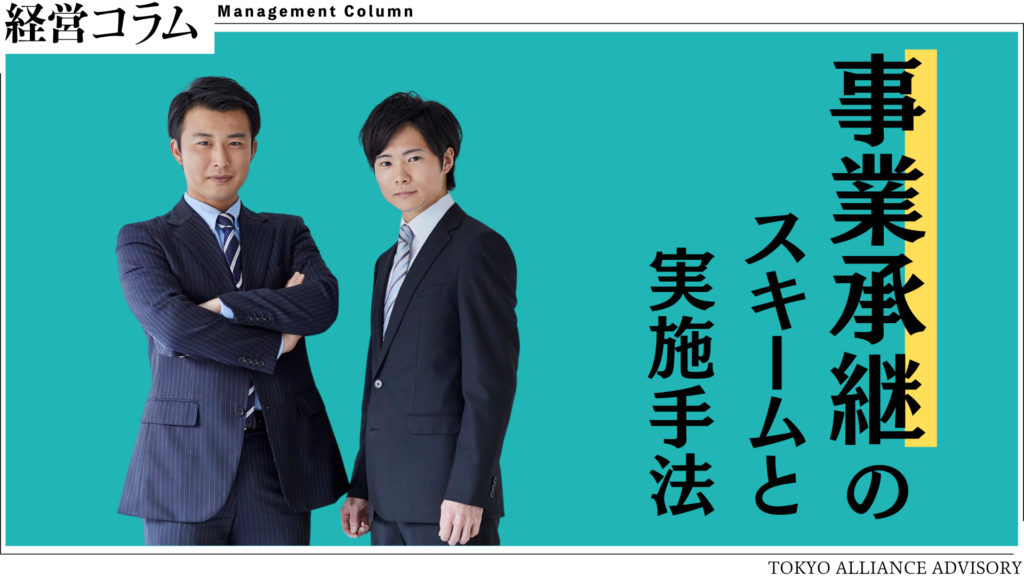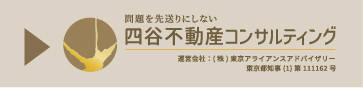事業承継の実施では、親族内承継・親族外承継・M&Aなどのスキームがあります。その実施手法も、株価対策、スムーズな承継計画の実行、後継者の資金状況などを総合的に検討して適切な方法を選択しなければなりません。ここでは、会社・事業の引き継ぎ方を俯瞰します。
事業承継スキームと選択のポイント
事業承継にはさまざまななスキームが存在し、自社の状況や後継者との関係によって最適な選択肢が異なります。もっとも多いのは現経営者の子どもや孫が継ぐ「親族内承継」ですが、従業員や第三者が承継する場合もあります。
親族内承継(同族承継)
親族内承継(同族承継)とは、経営者の子や配偶者、兄弟などの親族に事業を引き継ぐ方法です。2020年以降の5年間で代表者交代が行われた企業を調査したデータ※によれば、同族承継の割合は32.2%となり、徐々に減少しつつあるものの依然として根強く残るスキームです。
親族内承継の利点は、後継者を早期に決定することで、経営ノウハウの継承に時間を費やすことができる点です。血縁関係があるからこそ得られるメリットとして、創業者の理念、企業文化、取引先との関係などといった見えない資産の継承ができる点も挙げられます。
■親族内承継のメリット
- 経営理念や企業文化の継続性が高い
- 取引先や金融機関との関係維持がしやすい
- 長期的視点での経営判断が可能
- 準備期間を柔軟に設定できる
- 従業員からの心理的受容が得られやすい
一方で、親族内承継の実施面では、事業承継と経営者個人の生前対策を一体的に捉える必要がある点が課題となります。経営権の移転では「事業承継税制」などを積極的に活用しない限り、相続税および贈与税の負担が大きくなるといわざるを得ません。さらに、事業承継によって相続人のあいだで取得できる財産に不公平が生じ、トラブル化する懸念もあります。
■親族内承継の課題
- 相続税・贈与税の負担が大きい
- 後継者の経営能力不足のリスクがある
- 相続人間での財産分配の不公平によるトラブル発生
- 親族間での経営方針の対立が生じやすい
- 客観的な後継者評価が難しい
※参考:全国「後継者不在率」動向調査(帝国データバンク/2024年)
親族外承継(従業員承継)
親族外承継は、親族以外の人物、とくに従業員や役員に事業を承継する方法です。親族に適任者がいない場合や、能力や意欲のある従業員を活用したい場合に選択されます。
従業員承継を選ぶメリットは、後継者育成にかかる期間およびコストを従業員としてのキャリアで代替できる点です。業務に携わった人物が跡を継ぐのは取引先の心象が良く、社内でも従業員全体のモチベーション向上につながる期待があります。
■親族外承継のメリット
- 企業文化や業務内容の理解が深い人材を選べる
- 従業員全体のモチベーション向上につながる
- 取引先からの信頼継続が期待できる
- 能力本位の選定が可能
親族外承継の課題となるのは、具体的な実施方法です。MBO(経営陣による買収)やEBO(従業員による買収)などがあり、株式の段階的な譲渡や経営権の移行を計画的に進めます。このとき問題となるのは「後継者の資金状況」であり、金融機関からの融資や各種支援制度の活用が必要となるのが一般的です。
■親族内承継の課題
- 株式取得資金の調達が困難
- 個人保証の引継ぎに関する問題
- 経営者としての育成コストと時間が必要
- 株価算定の難しさ
- 現経営者の引退後の関与度合いの調整
- 現経営者の親族・ほかの従業員からの心理的受容
M&Aによる第三者承継
親族にも従業員にも後継者がいないときは、第三者に継承させる必要があります。その方法のひとつとして、M&A(企業買収)の活用があります。
M&Aのメリットは、後継者の選定および育成のための時間的・経済的コストをかけずに済むことだけでなく、企業価値に見合った売却対価を得られる点です。現経営者が得る対価は、自身のセカンドライフや、事業承継を希望しない子どもや孫に残す財産として利用できます。
■M&Aによる第三者承継のメリット
- 企業価値に見合った売却対価が得られる
- 後継者育成の時間と労力が不要
- 買い手企業とのシナジー効果による事業発展
- 従業員の雇用継続の可能性が高まる
M&Aのプロセスは、①準備段階(企業価値評価など)、②買い手の探索、③交渉・デューデリジェンス、④最終契約締結、⑤PMI(統合作業)の順に進みます。どの段階においても専門家による高度な支援が必要であり、ここで問題となるのが「レベルの高い専門家と出会えるか」です。
経営コンサルタントや士業による中小企業向けのM&A支援機関は増え続けており、2021年には登録制度が創設されました。もっとも、支援の方針や有資格者の状況は登録機関ごとに異なるため、慎重に比較・検討して自社の状況に合う専門家を選ぶ必要があります。
■M&Aによる第三者承継の課題
- 企業文化や経営方針の変更リスク
- 従業員の不安や反発への対応
- 秘密保持と情報漏洩のリスク
- 適切なM&A仲介業者選定の難しさ
- 売却後の経営者の関与度合いの調整
事業承継ファンドによる第三者承継
事業承継ファンドによる承継は、投資ファンドが一時的に株式を取得し、将来的な事業承継をサポートする方法です。後継者不在企業や事業再生が必要な企業に適したスキームとなっています。
ファンドから資金を得て事業承継を実施するメリットは、ファンドから派遣された経営のプロによる支援が受けられること、事業再生や成長を重視した承継が実現できることの2点です。
■事業承継ファンドのメリット
- 経営の専門家による経営支援が受けられる
- 段階的な承継プロセスが実現できる
- 成長投資のための資金調達が可能
- 事業再生や業績改善の機会となる
- 将来的な後継者育成の時間的猶予が得られる
事業承継ファンドによる計画の問題点は、通常3年から7年程度となる承継期間や、経営について一定の介入を受けることです。大前提として、ファンドの興味を引くには将来性のアピールが必要不可欠であり、相応の労力が求められます。
■事業承継ファンドの課題
- 投資回収期間が限定的(3〜7年程度)
- 経営への強い介入を受ける
- 高いリターンを求められる
- そもそもファンドの買収対象になるとは限らない
事業承継を実施するときの手法

実際に現経営者から後継者へと経営権を移転するときの手法には、株式譲渡や組織再編など手法が存在します。各手法の特徴を理解し、自社の経営状況や承継目的に合った方法を選択することが重要です。税務面や法的手続きの専門知識が必要なケースが多く、専門家の早期関与が成否を分けます。
株式譲渡(贈与・売買・相続)
株式譲渡は事業承継の基本的手法で、売買・贈与・相続の3形態があります。いずれの形態でも適切に株価を算定する必要があり、課税される場合は対策を講じなければなりません。
株式譲渡で積極的に利用したい税制優遇としては、直系尊属から直系卑属への贈与が対象となる「相続時精算課税」や、一定の要件を満たすことで納税が猶予される「事業承継税制」があります。事業承継税制では、株式譲渡が完了したあとの一定期間(承継期間)は雇用などの要件を満たす必要があるなど、さまざまな注意点があります。
持株会社・資産管理会社の設立
成長中の企業の事業承継では、持株会社を設立し事業を営む会社の株を保有させる方法が検討できます。不動産や特許権などの資産を抱える会社では、資産管理会社を設立して分離して節税に繋げる方法が考えられます。
現経営者が持株会社・資産管理会社を設立する事業承継スキームの利点は、株価に伴う課税額の上昇を抑えられる点です。現経営者の個人資産の評価は株式から譲渡益に変化することで固定され、事業を営む会社の株価上昇分は新説会社の含み益として吸収できます。新設会社の株価についても、株式取得のため融資によって上昇分を相殺することが可能です。
民事信託の活用
資金確保の見込みがあり、トラブルのないスムーズな承継の実現を重視する場合は、現経営者が保有する株式につき民事信託を利用する方法が考えられます。後継者を信託財産の管理者(委託者)とする内容で契約を組成し、合意で定めた所定の条件を満たしたときに信託財産(=株式など)の所有権が後継者に帰属する内容です。
民事信託の基本的なしくみは、株式の保有については現経営者に留保し、そこから経営権と受益権を分離させ、それぞれ後継者と後継者そのほかの当事者(相続人など)に付与するものです。現経営者が指導・監督するかたちでの段階的な承継を実現させつつ、配当で遺留分(※相続人に認められる最低限の権利)や後継者の納税資金を確保する体制を組めます。
まとめ
事業承継では適切なスキームおよび手法の選択が欠かせず、これにあたっては早期の自社分析と準備が求められます。後継者の有無・スキル・資金状況のほか、経営状況や将来予測にも適合した方法については、M&A支援機関のなかでも優れた経験と知識を有するものなどの支援が欠かせません。
株式会社東京アライアンスアドバイザリーは、経営面・資産面・心理面からの総合的アプローチを用いて、中小企業の事業承継や経営革新を支援する経営コンサルティング会社です。2008年の設立以来、ファミリービジネスへの深い理解と、経済産業省認定の経営革新等支援機関としての専門性を活かし、クライアントの持続的な発展をサポートしています。
会社・組織の将来について検討を進めたい方は、是非ご相談ください。