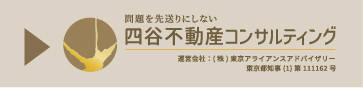コロナ禍を経て、多くの企業が事業環境の変化に直面しています。市場の縮小や消費者ニーズの変化、デジタル化の加速など、これまでのビジネスモデルでは対応しきれない課題を抱える企業も少なくありません。
こうした状況の中、国は「事業再構築補助金」という制度を通じて、企業の思い切った事業転換や新規事業の立ち上げを支援しています。特に今回の第13回公募は最終回となっており、これがラストチャンスとなる可能性もあります。
「新しい事業に挑戦したいが、資金面の不安がある」
「市場環境の変化に対応し、事業を再構築したい」
そんな経営者の皆様に向けて、本記事では事業再構築補助金の概要、対象となる事業の具体例、申請の流れを解説します。さらに、申請の成功率を高めるための専門的なサポートについてもご紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。
1.事業再構築補助金の対象者(誰が申請できるのか)
事業再構築補助金(第13回:最終回)は、新たな市場への進出や事業転換、事業再編を通じて成長を目指す中小企業および中堅企業を支援する制度です。
以下のような企業が対象となります。
補助金の対象となる企業
- 中小企業(資本金10億円未満、従業員数の上限あり)
- 中堅企業(一定の規模を持つが大企業には該当しない企業)
- 個人事業主や小規模事業者も対象になる場合あり(要件確認が必要)
どんな企業が活用すべきか?
この補助金は、以下のような企業に特におすすめです。
- 新規事業を始めたいが、資金面の負担が大きく踏み切れない
- 事業転換を検討しているが、リスクが高く踏み切れない
- ポストコロナの市場変化に対応し、新しいビジネスモデルを構築したい
事業再構築補助金は、企業の新たな挑戦を後押しする貴重な支援制度です。
補助対象となる要件を満たしているかを確認し、適切な準備を進めることで、成長のチャンスを最大限に活かすことができるでしょう。
2.基本的な申請要件
補助金を申請するには、以下の基本要件を満たしている必要があります。
- 「事業再構築」に該当する事業であること(事業再構築指針に基づく)
- 事業計画について、金融機関や認定経営革新等支援機関の確認を受けること
- 補助事業終了後3~5年間で、付加価値額の年平均成長率3~4%以上の向上を目指すこと
事業再構築の主要な要件
特に「事業再構築」の定義については細かい要件があるため、事前に確認しておくことが重要です。
ここでは代表的な要件3つを例に取り説明いたします。
1.新市場への進出、業種・業態転換、事業再編のいずれかに該当すること
- 例:飲食店がオンライン販売に参入、製造業が新たな分野の製品を開発するなど。
- ただし、単なる売上向上策や事業拡大のみでは対象外となる場合あり。
2.補助金の対象となる具体的な投資を伴うこと
- 例:新規設備の導入、建物の改修、システム開発、広告宣伝費などが補助対象。
- 人件費や不動産購入など、一部の経費は対象外。
3.事業計画における目標設定
- 付加価値額(=営業利益+人件費+減価償却費)の成長が求められる。
- 計画的な収益改善が必要で、申請時に事業計画を金融機関等に確認してもらうことが必須。
3.事業再構築補助金とは?(概要・金額・対象事業)
事業再構築補助金は、ポストコロナ時代に対応するため、新市場への進出や業種転換、事業再編を行う中小企業・中堅企業を支援する制度です。
これにより、企業が大胆な事業変革を行うための資金を確保し、成長を促進することを目的としています。
補助金額と補助率
| 事業類型 | 補助上限額(従業員30人の場合) | 補助率 |
|---|---|---|
| 成長分野進出枠(通常類型) | 3,000万円 | 中小1/2 / 中堅1/3 |
| 成長分野進出枠(GX進出類型) | 中小:5,000万円 / 中堅:1億円 | 中小1/2 / 中堅1/3 |
| コロナ回復加速化枠(最低賃金類型) | 最大1,500万円 | 中小3/4 / 中堅2/3 |
対象となる事業の種類
- 新市場進出:既存事業とは異なる新しい市場に参入(例:飲食店が食品加工・販売を開始など)
- 業種転換:現在の業種とは異なる業界へ転換(例:アパレル業がフィットネスジムを開業など)
- 業態転換:同じ業種内でビジネスモデルを変更(例:レストランがデリバリー専門に転換など)
- 事業再編:M&Aなどを活用し、企業の事業構造を変更
- 規模の拡大:新しい取組みを通じて企業の成長を目指す
この補助金を活用することで、企業は新たな市場に挑戦し、ポストコロナ時代のビジネス環境に適応することが可能になります。
4.具体的な対象事業のイメージ
事業再構築補助金は、幅広い業種・業態に対応しており、企業が新たな市場に挑戦するための支援を行います。ここでは、具体的な活用事例を紹介し、どのような事業が対象となるのかをイメージしやすくします。
5. 申請から事業終了までの流れ
事業再構築補助金の申請から事業終了までの流れは、大きく「事前準備」「申請・審査」「事業実施」「事業終了後のフォローアップ」の4つのステップに分かれます。
6.東京アライアンスアドバイザリーに相談するメリット
事業再構築補助金の申請は、単なる書類提出ではなく、戦略的な事業計画の策定と適切な申請プロセスの管理が求められます。そのため、専門家のサポートを受けることで、採択率を高めることが可能です。
東京アライアンスアドバイザリーでは、補助金申請から事業実施、事後フォローまで一貫した支援を提供しています。
① 採択率を高めるための専門的なアドバイス
補助金の審査では、事業の新規性や成長性、市場の適合性が重要視されます。東京アライアンスアドバイザリーでは、補助金の審査基準を熟知した専門家が申請書作成をサポートし、経営戦略と財務計画の両面から、事業計画の完成度を高めるアドバイスを提供します。審査では、どのような点が評価されるのかを考慮しながら、説得力のある申請書を作成することが重要です。
② 申請書類の作成支援(煩雑な手続きを代行)
補助金申請には、事業計画書や財務計画の作成、補助対象経費の算出など、多くの書類が必要です。これらの書類作成には専門的な知識が求められるため、経験のない企業にとっては大きな負担となります。東京アライアンスアドバイザリーでは、これらの煩雑な手続きをサポートし、電子申請(Jグランツ)をスムーズに進めるための支援も行っています。さらに、金融機関や認定支援機関との連携を支援し、より信頼性の高い申請書類の作成をサポートします。
③ 交付決定後の事業実施・報告支援
補助金は採択された後も、事業の進行管理や実績報告が求められます。交付決定後に適切な事業実施を行うことが重要であり、計画通りに事業を進めなければ補助金の受給が難しくなる場合もあります。東京アライアンスアドバイザリーでは、補助事業の進捗管理をサポートし、スムーズな事業実施ができるよう支援します。また、補助金の実績報告書作成についても、不備なく補助金を受給できるよう、専門家がしっかりとサポートします。
まずはお気軽にご相談ください!
補助金の申請はタイミングが重要であり、締切までの準備期間が限られています。
「うちの事業は対象になるのか?」「申請手続きが難しそう…」といった疑問や不安をお持ちの方は、ぜひ東京アライアンスアドバイザリーへご相談ください。
補助金申請のプロフェッショナルが、貴社の挑戦を全力でサポートいたします。
【関連書類のダウンロード】